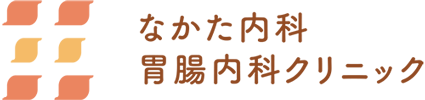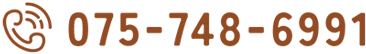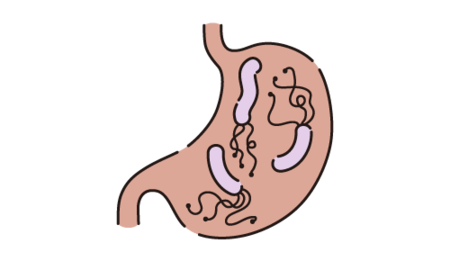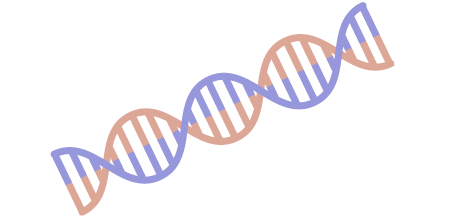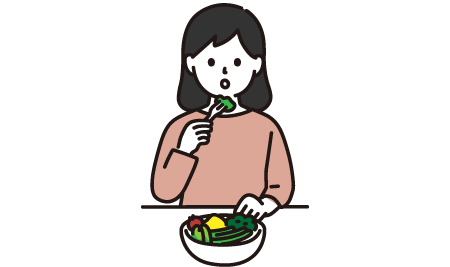2025.03.17
胃がんについて|初期症状・原因・治療方法の解説
胃がんとは?
胃がんは、胃の内側の粘膜に発生するがんです。初期には自覚症状がほとんどないため、早期発見が難しい病気の一つです。ヘリコバクター・ピロリ菌の感染や塩分の多い食事、野菜不足などの食生活、遺伝などが要因となります。
主な症状
初期にはほとんど自覚症状がありませんが、進行すると以下のような症状が現れることがあります。
- 胃の痛みや不快感
- 食欲不振
- 吐き気や嘔吐
- 体重減少
- 黒色便(タール便)
- 貧血
胃がんの原因と発症メカニズムについて
胃がんの発症メカニズムは複雑で、まだ完全に解明されているわけではありません。
また胃がんの発生には、複数の要因が複雑に関与しています。ピロリ菌感染は、胃がんの最も大きな原因の一つですが、他の要因も重要です。
早期発見・早期治療が、胃がんの予後を大きく左右します。
ヘリコバクター・ピロリ菌感染による慢性炎症
ピロリ菌が胃粘膜に感染すると、慢性的な炎症が引き起こされます。
慢性的な炎症は、胃粘膜の萎縮や腸上皮化生(胃粘膜が腸の粘膜に似た組織に変化する現象)を引き起こし、これらは胃がんのリスクを高めることが知られています。
食生活の乱れや喫煙、過剰な飲酒
塩分の多い食事は、胃粘膜を刺激し、ピロリ菌の活動を活発化させると考えられています。
また、ビタミンや食物繊維は、胃粘膜を保護する働きがあることから、野菜や果物の摂取不足も胃がんリスクを高めます。
その他、喫煙・飲酒や熱い食べ物や飲み物の過剰摂取なども、胃粘膜を刺激し、発がんリスクを高める可能性があります。
遺伝子異常の蓄積
遺伝子異常が蓄積すると、細胞の増殖を制御する機能が失われ、がん細胞が発生します。
がん抑制遺伝子の不活性化やがん遺伝子の活性化などが、がん細胞の発生に関与しています。
発生したがん細胞は、周囲の組織に浸潤しながら増殖していきます。
がんが進行すると、胃壁の深層に浸潤し、リンパ節や他の臓器に転移する可能性があります。
胃がんの発症率と患者層
胃がんは、一般的に50歳以降から発症リスクが高くなり、60代~70代ではでピークを迎えます。しかし、近年では若年層の発症も増加傾向にあります。
50歳以上
胃がんのリスクが顕著に高まる年齢層です。特に男性は、女性よりもリスクが高い傾向にあります。
60代~70代
胃がんの罹患率が最も高い年齢層です。定期的な検診が特に重要となります。
若年層(40代以下)
以前に比べると発症数は少ないですが、近年増加傾向にあります。
若年層の胃がんは、進行が早い場合があるため、注意が必要です。
胃がんの検査方法
内視鏡検査(胃カメラ)
先端にカメラのついた細い管を口または鼻から挿入し、胃の内部を直接観察する検査です。胃粘膜の状態を詳しく調べることができ、がんの早期発見に有効です。検査中に組織を採取(生検)し、病理検査でがん細胞の有無を調べることができます。
京都市のなかた内科・胃腸内科クリニックの胃カメラ(胃内視鏡検査)は、日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医である院長がを全て行います。
胃カメラ(胃内視鏡検査)に対して不安をお持ちの方にも安心して受けていただけるように、鎮静剤を使用した胃カメラ検査をおこなっております。患者さんが眠っている間に検査が終わりますので、苦しさや痛みを感じることなく胃カメラ(胃内視鏡検査)を受けていただけます。
詳しくは、胃カメラ検査のページをご覧下さい。
気になる症状がある場合、定期的に検査されたい場合など、お気軽にご相談ください。
胃X線検査(バリウム検査)
バリウムという造影剤を飲んでX線撮影を行い、胃の形や粘膜の状態を調べる検査です。
内視鏡検査に比べて負担が少ないですが、小さな病変の発見には限界があります。
異常が見つかった場合は、内視鏡検査で精密検査を行います。
その他の胃がん検査
その他にも胃がんの検査方法として、血液検査やCT・MRI検査、PET検査などがあります。
どの検査を受けるかは、年齢、症状、リスク要因などによって異なります。気になる症状がある場合は、早めに医療機関を受診し、医師と相談して適切な検査を受けましょう。
胃がんと似た症状の病気
胃がんと似た症状が現れる病気はいくつか存在します。これらの病気は、胃の不快感、痛み、吐き気、食欲不振など、胃がんの初期症状と共通する症状を引き起こすことがあります。
潰瘍・十二指腸潰瘍
胃や十二指腸の粘膜が傷つき、潰瘍ができる病気です。
胃痛、吐き気、胸焼けなどの症状が現れます。ピロリ菌感染や非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の服用が主な原因です。
胃炎(急性胃炎・慢性胃炎)
胃の粘膜に炎症が起こる病気です。急性胃炎は、急激な胃痛、吐き気、嘔吐などを引き起こします。
慢性胃炎は、持続的な胃の不快感、食欲不振などを引き起こします。ピロリ菌感染、ストレス、食生活の乱れなどが原因となります。
逆流性食道炎
胃酸が食道に逆流し、食道粘膜を刺激する病気です。胸焼け、呑酸(どんさん)、喉の違和感などの症状が現れます。
これらの病気は、胃がんの症状と似ていることがありますが、原因や治療法は異なります。自己判断せずに、医療機関を受診して適切な診断を受けることが重要です。特に、症状が続く場合や悪化する場合は、早めに医師に相談してください。
胃がんの治療方法
胃がんの治療法は、がんの進行度(病期)、患者さんの年齢や全身状態などを考慮して選択されます。主な治療法は以下の通りです。
内視鏡治療
早期の胃がんに適応されます。内視鏡を使ってがんを切除するため、開腹手術に比べて体への負担が少ないです。
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)などが代表的な治療法です。
手術(外科治療)
がんの進行度に応じて、胃の一部または全部を切除します。周囲のリンパ節も切除することがあります。
開腹手術、腹腔鏡手術、ロボット支援手術などがあります。
化学療法(薬物療法)
抗がん剤を使ってがん細胞の増殖を抑える治療法です。手術後の再発予防や、進行がんの治療に用いられます。
点滴や内服薬で投与します。
放射線療法
放射線を照射してがん細胞を死滅させる治療法です。進行がんの症状緩和などに用いられます。
免疫療法
免疫チェックポイント阻害薬などの免疫療法薬を用いて、がん細胞への攻撃を促す治療法です。一部の進行胃がんの治療に用いられます。
胃がんの予防方法
食生活の改善
塩分摂取量を減らすことで、胃炎膜の刺激を減らし、胃がんのリスクを低減できます。
また、バランスが取れており、規則正しい食生活を心掛けることで胃の負担を減らし、予防に繋がります。
禁煙・節酒
喫煙や飲酒は、胃粘膜の血流の悪化や傷つけることにより発がんリスクを高めます。
禁煙・適度な飲酒を心掛けることで胃がんリスクを減らすことができます。
定期的な検診
定期的に胃カメラ(胃内視鏡検査)などの胃がん検診を受けることで、早期発見・早期治療につながります。特に50歳以上の方は、定期的な検診をお勧めします。
まとめ
胃がんは、胃の内側の粘膜に発生するがんで、日本人にとって罹患率の高いがんの一つです。早期発見・早期治療が非常に重要であり、適切な予防法と検査、治療法を知っておくことが大切です。
胃がんは、発症初期の段階ではほどんど自覚症状がありません。進行すると、胃の痛みや不快感、食欲不振、吐き気、体重減少、黒色便などが現れることがあります。
気になる症状があれば、早めに医療機関を受診しましょう。京都市伏見区のなかた内科・胃腸内科クリニックの胃がん検査は、鎮静剤を使用し、苦しくない無痛の胃カメラ(胃内視鏡検査)を取り入れております。
患者さんが眠っている間に検査が終わりますので、苦しさや痛みを感じることなく胃カメラ(胃内視鏡検査)を受けていただけます。
日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医である院長による、正確で丁寧な検査・診察を行います。少しでも不安に感じられる場合は、ご相談ください。