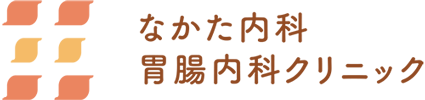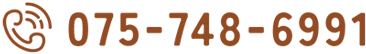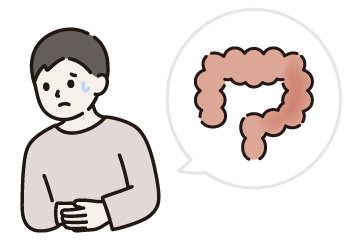2025.02.10
虚血性大腸炎に注意:検査から分かる初期症状と治療の流れ
虚血性大腸炎とは
虚血性大腸炎とは、大腸への血流が一時的に低下することで、腸管の粘膜に炎症が生じる疾患です。突然の腹痛や血便といった症状が現れるのが特徴で、高齢者を中心に発症することが多いです。
この疾患は、虚血性腸疾患の中で最も一般的なものであり、軽症の場合数日で回復することも多いですが、重症化すると腸管の壊死を引き起こす場合もあります。
主な症状
- いきなり強い腹痛が起きた
- 左下腹部が痛むケースが多い
- 下痢・軟便
- 冷や汗や吐き気、嘔吐がある
- 水もしくはゼリー状の下痢・血便がでてきた
発症メカニズム:大腸への血流障害
虚血性大腸炎は、大腸の血流障害によって発症します。腸管の血流が一時的または局所的に減少すると、酸素や栄養の供給が不足し、粘膜が損傷を受けて炎症を引き起こします。この血流障害の原因の一例として、動脈硬化や高血圧などが挙げられます。また、便秘や排便時の強いいきみによって腸管への血流が遮断されることも発症の引き金となります。
発症率と患者層:高齢者に多い理由
虚血性大腸炎は主に高齢者に多く発症する疾患です。その理由は、高齢者において動脈硬化、高血圧、糖尿病などの基礎疾患を抱えることが多く、これらが大腸への血流障害を引き起こすリスクを高めるためです。
また、加齢による腸管の血管壁の弾力性低下や便秘傾向も関与しています。
典型的な患者層として、60歳以上の便秘がちの女性が挙げられます。一方で、最近では若年層の患者も増加しており、特にストレスや偏った食事が原因となるケースが報告されています。
虚血性大腸炎と他の腸疾患の違い
虚血性大腸炎は、他の腸疾患といくつかの点で特徴が異なります。たとえば、大腸がんや炎症性腸疾患(クローン病や潰瘍性大腸炎)は、多くの場合慢性経過をたどりますが、虚血性大腸炎の多くは一過性で数日から1週間で回復が期待できます。
また、血便の色合いが「いちごジャム状」など特徴的で、診断の手がかりとなることがあります。さらに、発症メカニズムも異なり、虚血性大腸炎は血流障害が原因であり、それ以外の腸疾患は炎症や感染が原因となる場合が多いです。しかし、症状には共通点も多いため、大腸カメラ(大腸内視鏡検査)を用いて鑑別診断を行うことが重要です。
虚血性大腸炎の原因とリスク要因
01.血管側の要因: 動脈硬化や高血圧
虚血性大腸炎の主な原因の1つが血管側の問題です。大腸への血流が低下する要因として、動脈硬化や高血圧が挙げられます。動脈硬化は血管内の壁にコレステロールや老廃物が蓄積することで血流が妨げられる疾患で、高血圧などの生活習慣病が進行すると血管の弾力性が低下し、血流障害が起こりやすくなります。
このような状態が続くと、大腸の一部が虚血状態に陥り、炎症や壊死が発生することがあります。特に高齢者においては、動脈硬化が進行していることが多く、虚血性大腸炎の発症リスクが高まります。
02.腸管側の要因: 排便時のいきみや便秘
腸管側の要因としては、排便時の強いいきみや慢性的な便秘が挙げられます。便秘により腸内に便が滞留すると腸内圧が高まり、その結果、血流が阻害される場合があります。また、強くいきむことによって腹腔内圧が一時的に急上昇し、大腸内の血流が遮断されやすくなるのも危険な要因です。
これらの状況が続くことで、大腸粘膜が正常な機能を果たせなくなり、虚血性大腸炎の症状が引き起こされる可能性があります。便秘に悩む患者では、日頃の排便管理が重要です。
03.生活習慣と食生活の影響
生活習慣や食生活も虚血性大腸炎の発症に深く関与しています。脂肪分の多い食事や食物繊維の不足は、腸内環境を悪化させるだけでなく、動脈硬化や便秘を引き起こす原因にもなります。また、不規則な食事や過度な飲酒、喫煙も血管や腸管の健康を損ない、虚血性大腸炎を発症するリスクを高めます。バランスの良い食事を心がけつつ、水分をしっかり摂取することで腸内環境を整えることが重要です。
04.ストレスや体調不良が引き金になる場合
ストレスや体調不良も虚血性大腸炎の発症に関係します。ストレスが強いと自律神経のバランスが崩れ、血管が収縮しやすくなります。この結果、大腸への血流が低下し、炎症を引き起こしやすくなります。また、過労や体調不良が重なると免疫機能の低下が起こり、それが虚血性大腸炎のリスクを高める一因となることもあります。高ストレスな環境や不規則な生活は腸に負担をかけるため、適切な休息やリラクゼーションを取り入れることが予防策として有効です。
虚血性大腸炎の初期症状と診断の流れ
突然の腹痛と血便のサイン
虚血性大腸炎の初期症状として最も多く報告されるのが、突然の腹痛や血便です。特に左下腹部の痛みを訴えるケースが多く、これは血流障害が主に大腸の左側で発生しやすいためです。血便については、鮮血混じりの場合もあれば、「いちごジャム」のような特徴的な色合いで現れることもあります。また、腹痛以外に下痢や冷や汗、嘔吐を伴う場合もあるため、これらの症状が見られた際は虚血性大腸炎の可能性を疑い、早急に医療機関を受診することが重要です。
診察での質問例と初期確認事項
診察においては患者さんの生活習慣や症状について詳しく質問します。「いつから腹痛が始まったか」「血便の有無やその色・頻度」「便秘や下痢を繰り返しているか」などといった質問です。
また、高血圧や動脈硬化症、便秘の既往があるかどうかといった患者の健康状態も確認させていただきます。
丁寧に問診を行うことでストレスや食生活といった虚血性大腸炎のリスク要因を洗い出していきます。
虚血性大腸炎の検査について
虚血性大腸炎の診断を確定するためには、いくつかの検査が必要です。まず血液検査では、炎症を示す数値(例えばCRPの値)が上昇しているか確認されます。腹部エコーでは、大腸の粘膜の様子を確認でき、虚血性大腸炎特有の病変を確認できます。
さらに確定診断には、大腸内視鏡検査が有効です。内視鏡検査では腸内を直接観察し、粘膜の発赤、浮腫、びらん、または潰瘍の有無を確認します。内視鏡検査は確定診断に不可欠ですが、粘膜の状態が改善している場合には異常が見つからないこともあります。
京都市伏見区のなかた内科・胃腸内科クリニックでは、AIによる病変の検出支援機能を搭載した大腸カメラを導入しています。AIによる検査画像の膨大な学習により、病変を検出する感度96%、特異度98.0%の診断支援精度を誇ります。
詳しくは、大腸カメラ検査のページをご覧下さい。
虚血性大腸炎以外の他の疾患の可能性は?
虚血性大腸炎の症状は、大腸憩室炎や感染性腸炎、さらには大腸がんといった他の腸疾患とも似ているため、これらを区別する鑑別診断が必要です。特に高齢者では複数の疾患が併存している可能性があり、血便や腹痛の原因が一概に虚血性大腸炎とは限りません。
鑑別のためには、症状の出現パターンや検査結果を総合的に判断します。内視鏡検査、さらには病理組織検査(必要に応じて)を併用することで、より正確な診断が行われます。
虚血性大腸炎の治療方法と回復へのステップ
軽症の場合:絶食と輸液による対応
軽症の虚血性大腸炎は、多くの場合、非侵襲的な治療法で改善が期待できます。治療の基本は、腸に休息を与えることです。まず絶食を指示されることが多く、飲食を控えることで腸への負担を軽減します。同時に、体内の水分や栄養素を補うために、静脈から輸液(点滴)が行われます。また、症状が軽快するまで安静を保つことも重要です。このような初期の対応によって、多くの患者は数日内に回復へ向かうケースが多いです。
重症例の入院管理と経過観察
重症の場合は、入院治療が必要となります。重症例では腹痛や血便の症状が強く現れるため、経過を慎重に観察する必要があります。入院中は、患者の血行動態を安定させるための集中管理が行われ、必要に応じて抗生物質の投与も検討されます。また、血液検査やCT検査を用いて症状の進行具合や大腸の血流状態を随時確認しながら治療方針を調整します。特に壊疽型の可能性がある場合は、迅速な対処が求められます。
まれに薬物療法や外科的処置の必要性があるケースも
症状が進行し、壊疽型や狭窄型に移行する可能性のある場合には、薬物療法や外科的処置が必要になることもあります。例えば、感染のリスクが高い場合には抗生物質が使用されることがあります。さらに、大腸の一部が壊死していたり、腸管が閉塞している場合には外科的手術が必要になります。このような場合、壊死した部分を切除することで症状の改善を図ります。幸い、このような外科的治療が必要なケースは虚血性大腸炎全体の中では少数です。
虚血性大腸炎の治療後の再発予防とアフターケア
治療後に症状が改善したとしても、虚血性大腸炎には再発のリスクが伴います。そのため、再発予防を目的としたアフターケアが重要です。便秘を予防するために、食事の見直しや水分摂取の管理が基本となります。また、適度な運動を取り入れることで血流を改善することも有効です。ストレスの管理も大切で、体調不良が引き金になることを防ぐために日頃から無理をしない生活を心がけましょう。このような生活習慣の改善を通じて、再発のリスクを減らすことが期待されます。
予防策と生活習慣の見直し
食事の工夫:便秘を防ぐための食生活
虚血性大腸炎の予防には、便秘を防ぐための食生活が重要です。食物繊維を豊富に含む食品を積極的に摂取し、腸内環境を整えることが求められます。具体的には、野菜や果物、全粒穀物、豆類などが効果的です。また、水分摂取が不足すると腸内環境が悪化し便秘に繋がるため、1日あたり1.5〜2リットルの水を飲むよう心がけましょう。一方で、脂質や動物性食品の過剰摂取は血液をドロドロにし、動脈硬化を助長する可能性があるため控えめにする必要があります。バランスの取れた食事が便秘を防ぎ、虚血性大腸炎の原因となる血流障害のリスクを下げる鍵となります。
適度な運動習慣の重要性
日常的に適度な運動を取り入れることは、虚血性大腸炎のリスクを減らす大切な要素です。散歩や軽いジョギング、ストレッチなどの有酸素運動は腸の動きを活発にし、便秘を予防します。また、運動は血液循環を促進し、血流障害によるリスク低減にも役立ちます。長時間座りっぱなしの生活が多い人は、1時間に1度立ち上がり身体を動かすなど、生活の中に無理のない範囲で積極的に運動を取り入れましょう。ただし、無理な運動や過度な負荷は逆効果になることもあるので注意が必要です。
生活習慣改善のポイント
規則正しい生活を送ることは、虚血性大腸炎の予防に直接的な影響を与えます。まずは毎日の睡眠時間を確保し、体内リズムを整えることが大切です。不規則な食事や偏った栄養摂取、過度な飲酒や喫煙は、動脈硬化や便秘を引き起こし、腸への血流障害に繋がる可能性があるため避けましょう。さらに、食事の摂取タイミングを一定にする習慣を身につけると、腸内環境が改善し、腸管への負担を軽減できます。生活の中で小さな改善を積み重ねることで、身体全体の健康維持に繋げることができます。
まとめ
虚血性大腸炎は、年齢が高くなるにつれて発症すること増えますが、最近はストレスや食生活等の環境の変化に伴い若い方の発症も増えています。
もし、いきなり強い腹痛や下痢が起きて、吐き気や嘔吐、血便などの症状があれば、虚血性大腸炎の可能性が考えられますが、他の疾患であることもありますので、出来るだけ早い段階で消化器内科を受診して検査を受けることをお勧めします。
当院では、わずかな病変も見落とすことが無いようにAIによる病変の検出支援機能を搭載した大腸カメラを導入しておりますので、他の疾患の可能性も含めて検査をすることができます。