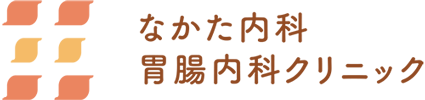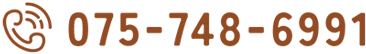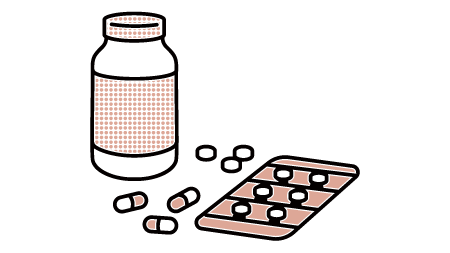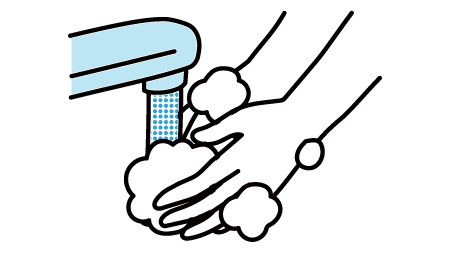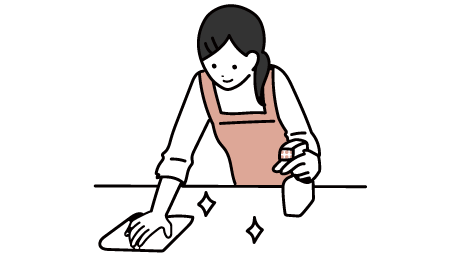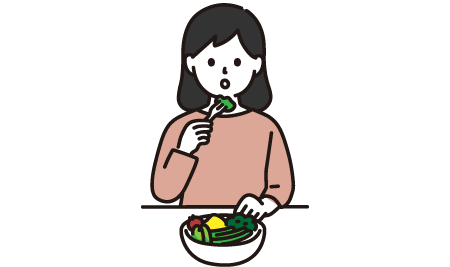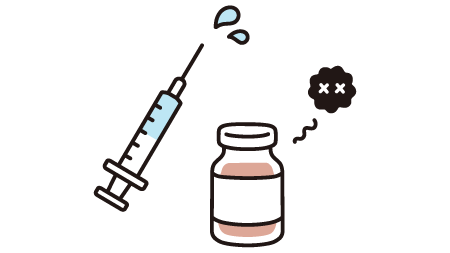2025.04.08
急な腹痛、嘔吐は感染性腸炎かも?潜伏期間、症状、予防の全てを解説
感染性腸炎とは?
感染性腸炎は、ウイルス、細菌、寄生虫などの病原体が腸管内で感染・増殖し、炎症を引き起こす疾患のことをいいます。主な感染経路としては、汚染された食品や水の摂取のほか、感染者の嘔吐物や便に触れてしまった場合などが挙げられます。また、人やペットから直接感染することもあります。
病原体によって異なりますが、一般的には細菌性腸炎は夏季に、ウイルス性腸炎は冬から春にかけて多く発生します。
乳幼児や高齢者は、脱水症状を起こしやすく重症化することがあるため注意が必要な病気です。血便や高熱、激しい腹痛などの症状がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
病原体別、感染性腸炎の特徴と症状
感染性腸炎の主な症状は、原因となる病原体によって、症状の現れ方や重症度が異なります。以下に、代表的な病原体ごとの症状をまとめました。
ウイルス性腸炎
ウイルス性腸炎は、ウイルス感染によって引き起こされる腸の炎症で、主にノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルスなどのウイルスが原因となります。
主な感染経路として、感染者の嘔吐物や糞便や汚染された食品や水の摂取、飛沫感染などがあります。
ウイルス性腸炎の主な症状
- 嘔吐
- 下痢
- 腹痛
- 発熱など
細菌性腸炎
細菌性腸炎は、細菌感染によって引き起こされる腸の炎症であり、「食中毒」ともいわれています。汚染された食品(生肉、生魚、加熱不十分な食品など)や水の摂取や、感染者の糞便からの経口感染などが主な感染経路です。
細菌性腸炎の主な症状
- 腹痛
- 下痢
- 嘔吐
- 発熱
- 血便など
寄生虫性腸炎
寄生虫性腸炎は、寄生虫が腸管内に寄生することで引き起こされる腸炎です。汚染された水や食品の摂取のほか、寄生虫に汚染された土壌との接触、感染者の糞便からの経口感染などが主な原因となります。寄生虫の種類によっては、潜伏期間が長いことから感染に気づきにくく、さらに一部の寄生虫感染症は慢性化し、長期にわたって症状が続くことがあります。
寄生虫性腸炎の主な症状
- 下痢
- 腹痛
- 吐き気
- 嘔吐
- 体重減少
- 血便など
感染性腸炎の潜伏期間
感染性腸炎の潜伏期間は個人差があるほか、感染しても症状が現れない不顕性感染の場合もあります。
また、原因となる病原体によって症状や重症度が大きく異なるため、症状が現れた場合は、自己判断せずに医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが重要です。
ウイルス性腸炎
- ノロウイルス:1~2日
- ロタウイルス:2~4日
- アデノウイルス:3~10日
細菌性腸炎
- サルモネラ菌(卵および卵製品、洋菓子類、加熱不十分な食肉等):
6時間~3日 - カンピロバクター菌(鶏肉、牛生レバー、殺菌不十分な井戸水):
2日~7日 - 腸管出血性大腸菌(弁当や給食等を要因とする事例が多い):
3日~8日 - 腸炎ビブリオ(魚介類の刺身、すし類):
6~24時間
寄生虫性腸炎
- アメーバ赤痢:数日から数週間
- ジアルジア症:1~2週間
感染性腸炎の治療法
感染性腸炎の治療は、原因となる病原体や症状の程度によって異なります。主な治療法は以下の通りです。
対症療法
ほとんどの感染性腸炎は、安静と適切な水分補給で自然に治ります。
下痢や嘔吐によって失われた水分と電解質を補給することが最も重要です。経口補水液やスポーツドリンクなどを少量ずつ頻繁に摂取しましょう。脱水症状がひどい場合は、点滴による水分補給が必要になることがあるため、医療機関を受診してください。
また症状が落ち着くまでは、消化の良い食事(おかゆ、うどん、りんごなど)を摂り、脂っこいものや刺激の強いものは避けましょう。
薬物療法
感染性腸炎の原因が細菌や寄生虫の場合、抗菌薬や駆虫薬を投与することがあります。
しかし自己判断での薬の使用は、腸内細菌のバランスを崩し症状を悪化させる可能性があるため、必ず医師の指示に従ってください。
入院治療
脱水症状がひどい場合や、重症化した場合は、入院治療が必要になることがあります。
感染性腸炎の予防について
感染性腸炎の予防は、日頃の心がけと適切な対策が重要です。以下の対策を徹底することで、感染性腸炎のリスクを大幅に減らすことができます。
手洗いの徹底
感染予防の基本は、丁寧な手洗いです。特に、トイレ後や調理・食事の前、外出後、嘔吐物や便の処理後などは必ず、石鹸と流水で指の間や爪の間も丁寧に洗いましょう。
一方アルコール消毒は、ノロウイルスなど一部のウイルスには効果が低いので、流水での手洗いが推奨されます。
食品の衛生管理
野菜や果物はよく洗い、生ものの食品は十分に加熱しましょう。また、生肉や魚介類を扱った後の調理器具は十分に洗浄・消毒することもとても重要です。
さらに食品の保管は、種類に応じて適切な温度・方法で行い、冷蔵・冷凍庫の温度管理を徹底しましょう。
家庭内での二次感染予防
家庭内に感染者がいる場合は、タオルや食器の共用を避け、トイレやドアノブなどのよく触れる場所はこまめに消毒しましょう。
また感染者の下痢や嘔吐物の処理は、乾燥するとウイルスが空気中に漂い感染を広げる原因となるので、乾燥する前に処理することが大切です。
そして感染者は、症状が治まるまでは調理を控えましょう。
免疫力を高める
免疫力を高め、感染しづらい身体をつくることも予防策の1つです。
バランスの取れた食事や十分な睡眠、適度な運動を心がけ、免疫力を高めましょう。特に、乳幼児や高齢者は、感染すると重症化しやすいので、注意が必要です。
ワクチン
ロタウイルスにはワクチンがあります。乳幼児は定期接種として受けることができます。
まとめ
感染性腸炎にかかったら、下痢や嘔吐によって失われた水分を補給するために、スポーツドリンクなどの水分補給を徹底し、安静にしましょう。
高熱や激しい腹痛、嘔吐、下痢などの症状が続く場合は必ず医療機関を受診し、医師の指示に従ってください。自己判断で市販薬を服用すると、症状を悪化させる可能性があります。
また病原体によっては、感染力が非常に強い場合があります。そのため手洗いの徹底や、タオル・食器の共用を避けるなど、周囲への感染を防ぐために注意しましょう。